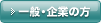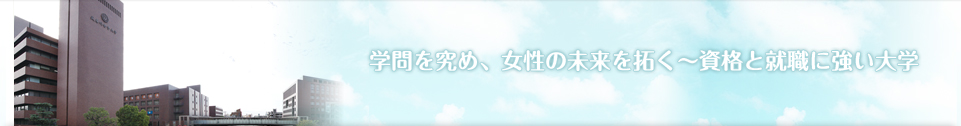
80üNLOvCxgúM@«ê©çpX|[gðg¦Ä\\ÀkïuZåñ«êÒvJÃ[2018/01/12XV]


@«êªÜ¾AJ¡ºÉ Á½ºa30`40NãBüwSð¹ÉApX|[gðg¦ÄÉìqZúåw2Éiwµ½w¶½¿ª¢½BAq³çÌ[Xe[WÍZåÉ Á½Bܾ«Ìiw¦ÍáA«Èªçw×é2ÍlCª Á½BÉìw@ͱ¤µ½j[Yð¢¿Lb`B1950NAZåJÝƯÉéÔÌ2ðJuµ½Bí©çãp³õƵijdɧÁÄ¢½«½¿ªA³®ÈÆðæ¾·×ʤP[Xªß̤¿AÚ§Á½BZåÌ2NÔųõÆðͶßAlXÈiªæêéwZÍÈ©Á½B
@«ê©çÌiwÒÉà»ê¼êÌîª Á½BíÅ[¢½«êÍAíã20N½ÁÄàAxoϬ·É¦{yɧ¿xêÄ¢½BZÉiÝAåwiwðó]·éw¶à¢½ªA«êÉåwªÈ©Á½B»ñÈÂÇóÔÌAu«ÈªçiwµA³õâÛçmÌiðæ¾Å«éæ¤ASÊIÉT|[g·évÆ¢¤éƪ»ê½BÉOsÌuqÑGNgHÆv()B1966NAæèæ¢lÞðßIJÒÉ^[QbgðièA«êÉlÉæèoµ½B¯ÐÍAÉìqZúåwðͶßAã_Ô̢©ÌwZɦÍðËB¾â}oXà®õµ½Bw¶Íó]·éwZÉʢȪçA¢½¿©çwïð¥¢A2NÅ̽ÉAÁijdɧ±ÆàÂ\\\B^ÈÊ¿ÅlSÒÌbÉ·«üÁ½w¶Ì½ªA±ÌéÆÉAEµ½B
@«ê©çDÅ3úBpX|[gð¬èµßA_Ë`©ç¼{sàÖBßÄÌ{yÌL¯ÍAÁ«ª¢ÁÏ¢¾Bu
µ½úAݼêª~ÁÄ¢½BúÉÍXª£ÁÄA¤êµ³É¦³ðYê½vußÄ~cÉo½Æ«A¡fà¹Ìl̽³ÉA«ª·ñ¾vuÖ¼ÌlªJ[ɶð©¯éÌÅÑÁèµ½v\\BdÍaÑ©gݧÄÌ¢¸ê©ÅAßO7©çßã4ÜÅB[HðÆèAoXÉæèñÅLpXÉü©¢Aßã9AoXÅw¶¾ÉAéB¾Í4lA5l¯ºBdÆw¶Ì2d¶Í í½¾µß¬A²Æ©ç45Nªoßµ½B
@1988NÉððI¦Âwµ½Zå2ÍAw@ÌWÉå«È«Õðcµ½BS©çWÜÁ½2w¶ðã\µA1962N©ç1972NɲƵ½«êogÒ5¼ÆAw@·Aw·ÉæéÀkïuZå2«êÒvª2017N1120úAsíê½B
u¨©¦èȳ¢v\\B²Æ¶ÀkïÍ¢ÂàA
ì¼Sw·ÌA±Ì¾tÅnÜéBåÍ´Êw@·Íuw@WúÌC éL¯ðA80üNÌßÚɺÐL¯ÉÆÇß½¢vÆÄÑ©¯½B
@QÁÒÌÅêÔæyÌîäõq³ñ(ÆȲ)ÍAܾqÑGNgªlÉæèo·ÈOAòèsÌfêîÉZÝA«ÈªçZå2ÉÊÁ½Bu³õÉÈ轢Ƣ¤¾mÈÚIª èܵ½BA¯¶wÈ̯¶Í30lÙÇŵ½ªA»Ì¼Íãp³õ©çø«±«³dɧ¿A³®È³õÆð¾æ¤ÆÊwµÄ¢él½¿Åµ½vBîä³ñÍA®
{ªsµ½pX|[gÆAú{{ÌgªØðåØÉÛǵĢ½BF ¹½ñûð¦µAuAOÍ¢ëñȧñª èܵ½BÖ¼ÜÅ¡Èçòs@ÅÐÆÁµÑÅ·ªA£ÈãÉ´¶çêܵ½vƾ¤Bîñs«©çA«êÉηéΩà Á½Bu«ÈªçwÔÌ͵µ©Á½¯êÇA»êðæèz¦½Ý͡ɶ«Ä¢Ü·B«êÉ¢ÄÍA©·«Å«È¢L¢¢EÉGêé±ÆªÅ«½B\Ì©ûà{yÅßÄmèAãXAo£ÌÛÉA¸¢Ôñð§¿Üµ½Bwméx±ÆA̱·é±ÆÍÀÉÍ¢ÈAÆv¢Ü·vB²Æãͫ꧳çÏõïÅèNÜųçsÉgíèAÞEãÍAK[XJEgÌw±âqçÄx{eBAÅÐïÆÂȪÁÄ¢éB
@¬´ìDü³ñ(³çȲ)àAu³õÉÈévÆ¢¤¢ÓuÅåwiwðÚwµ½ÐÆè¾B®
åwÌÄó±ðÀÁÄ¢½Æ«AZÌiHw±ºÅqÑGNgÌlà¾ðó¯Au2NųõƪæêéÈçvÆAòÑ¢½B»Ì¢ÓuðÑ¢ÄA«êŬwZ³õÆÈèAZ·ÜÅÎß½B
@¢a}³ñ(³çȲ)ͬ´ì³ñƼìZ̯¶B»ëÁÄÉìÉiwµ½Bu³EÉKvÈÌÅAGÁ½±ÆàÈ¢sAmðKÉûKµ½Ìðo¦Ä¢Ü·vB²ÆãAåãsàÌct³@ðÎßAÔÒ¼ãÌ«êÉAÁÄ©çÍAÅìèƵÄfÃαð62ÎÜű¯½Bu³õÆÍ᤹ðàñ¾¯êÇA³õƪ é±ÆÅADZÖsÁÄàFßÄàç¦ÄA©MÉÈèܵ½BsïÌXs[h´Éµê½¨©°ÅA«êÅÍweLpLæxÆ]¿³êéæ¤ÉÈèܵ½vÆΤB
@gÆÝq³ñͶȲB®
åwÖÌiwª©Èí¸Aiµ½ßesðÌÌpÊmàÈAãXƵĢ½Æ«AEÀÅqÑGNgÌlðmÁ½BuÌÄé_ êÎE¤_ èAÆ¢¤v¢Åµ½Bæ¶ÉÈ轢Ƣ¤æèAܾwÑð±¯çêéA©ªÌꪾçêéAÆ¢¤ìѪ嫩Á½B2NÔAéÆÉççêÄAxÞ±ÆÈwÆÉãÝܵ½vB«êÉAÁÄ2NÔAÏõÆÉgíÁ½ãAö¶®³ºðJݵ½B
@Sõª³õÆðèÉ̽ÉAÁ½ªAK¸µàæ¶ÉÈÁ½í¯ÅÍÈ¢Bxq³ñ(íȲ)ÍA³çÀKÅ̬³È¸sªSÉÐÁ©©èAdzõÉÍÈçÈ©Á½ªA³õÆæ¾Æ¢¤ÚIÉü©ÁÄw͵AÚIðB¬µ½±ÆÍA©MÉÈÁ½BuéÔÌwZÁÄåϾÁ½Åµå¤AƾíêÜ·ªAÇ¢æ¶AæyAÔÉbÜêAÉÆÁÄÍSeÞAyµ¢w¶¶Åµ½Bl¶ÅêÔ×µ½2NÔÅ·vB
@
@ÀkïÉÍA²Æ¶Ì¤¿4¼ÌÌpðSµ½³qÑGNgÌåe¸³ñàQÁµ½Buåe³ñÆÌoȯêÎAÉìƽ¿ªÂȪé±ÆÍÈ©Á½BêZðKËéOÉAê¾äçð¾¢½¢vÆAg³ñªceðÁÄTµoµ½Båe³ñÍQÁÒçÆÀkïúA40NÔèÌÄïðʽµAu²Ìæ¤B»És«évÆìñ¾BÀkïÅÍAéÆlÌÚüÅAÌ«êÌóµâA×wðT|[gµ½^ÓðêÁ½B
@uqÑGNgÍAaÑÆeídq@íÌJAWIÌgݧÄÈÇðµÄ¢Üµ½Bª«êÉlÉæèoµ½ÌÍ1966NtB·ÅÉ«êÍÏõqÅɬíÁĢܵ½ªAØâ©ÈÛÊèÌêØ ÉÍAobNɽ¢ÑàªÐµß«éçµAxOÉÍíÅåð¸Á½ó«Æª_ݵÄAlXÈâèðàï·é»Àª èܵ½B»Ìæ¤È«êÌ«ðl¦½Æ«Aá¢lª{yÉÄHêÅ¢ÄàA»Ìo±¾¯ÅÍ̽ÉAÁĽÌðÉ৽ȢB«ÈªçÆð¨yYÉAÁÄàç¢A«ê̽ßÉð§ÄÄÙµ¢AÆl¦½ÌÅ·vB
@¬Aã_ÔÌÊwÂ\ÈZɦÍðËB»ÌÉÉìqZúåwà Á½B
uÌúºWw·ÉÊïµA«êÌóµð¨bµÜµ½Bw·Í[¤È¸©êAwºÐA{wɤ¢¢qðAêīľ³¢A«êŨðɧÂæ¤A³çÍäXŵÁ©èâèÜ·©çxÆA¨ÁµáÁÄ¢½¾«Üµ½vÆUèÔéB
@Sõª²ÆãAͶßÄÌêZ¾Æ¢¤B·Á©èlÏíèµ½LpXÉAÌw@Ìlqâæ¶Ìv¢oÉàbªyñ¾B
@³ñÍA ééAÊwoXð~èéÆAØ¢ZÉ̺É[[ªÍßÜêéÌðÚµ½BCÉÈèȪçöÆÉü©¢AAèÛÉÄÑ©éÆAæÙÇÌZɪÕ`àÈ¢Buæèó³ê½í¯ÅàÈ¢ÌÉAêṳ¿ÉÈÈÁ½ÌÅÑÁèµÜµ½vB±êÉεAåÍ´w@·Íu»êÍw@LOÙÅ·æBwZą̃ÌêÅAºaVcªsK³ê½Æ«Ax_ɧ½ê½LǪÈÌÅA¡àwàÉÚ]µÄcµÄ éñÅ·vÆí¾©µðµ½B
@îä³ñÍA2ÌåC³õÌv¢oðêÁ½Bu2Ìw¶Éðª éæ¶ÅA¢ë¢ëÈkÉæÁÄê½BCw·sÉs¨àªÈ¢w¶ÉÍwlªÝµÄ °éæAÝñÈÅs±¤æxƾÁĺ³¢Üµ½vB
@¼ïÌ«êxÉͯïõª80¼¢éBÅßÍ«êÉ ±ªêÄAÚZµÄé²Æ¶à¢éÆ¢¤B«êx·ð±ß鬴ì³ñÍu«êÅÖ¼ogÌlÉwÉ̲ÆÈÌæxÆ¢¤ÆAw¢¢wZæËxÆÙßçêéÌÅA©MðÁľÁĢܷvA¢³ñÍubq
êªerÉféÆAÉìw@ÌLª©¦Äw AêZªoÄéxƤêµÈèÜ·vÆAêZ¤à Óê½B
@w¶©çuZ²ÆãA§OÌåwÉiw·élͽ©Á½ÌÅ·©vunû©çá¢lªsïÉoÄ¢ÌÍAn³ÉÆÁÄ}CiX¾Á½ÌÅÍvÈÇA¿âàòÑoµAÀkïÍMCÉïÜê½BÅãÉåÍ´w@·ªu«ê©ç½³ñÌw¶ªÄêéæ¤ÉAè¾Äðsµ½¢vÆÄÑ©¯éÆAuAJªZÈÇÛ»ðiµÄ¢é±Æð²µÄÍvu¾ª éÈç«ê©çiwµâ·¢vuZâmÉîñðñµÄvÆA²Æ¶©çAhoCXª¢¾B
@
(Ä)
næÆÆàÉ1\\¹yw@èútï[2017/12/19XV]


@åwÌg½ÌêÂÉunæÖÌv£vª éBÉìw@Ìnæv£ÌðjÍ¢ÂnÜÁ½Ì©B
@®OðKvÆ·éwÌÁ«ãA¹ywÍnæv£Éea«ª¢B»ÌN̳ç¬Êð\·éèútïÍLêÊÉöJµA50NÈãÌðjðdËÄ«½B
@æ1ñÌèútïÍA1963N111úÉJÃBºyEÌdÁ¾Á½ØºÛ³öª1`4N¶SõÉæé¥ðwöµ½B1980N²ëÜÅA[ÍsAmºtÉæ麥¾Á½BAXe[WÅ
pµÄ¢½^ÁÌOhXÍAw¶ÌÔÅgCJhXhÆÄÎêAeµÜê½BïêÍA_ËÛïÙÈÇAwOÌz[ðpµA³õªt·é±Æà Á½(Ê^EÍ1967NAæ5ñèútï)B
@ßNÍö]LOu°ðïêÉAI[PXgÌÝÌÈÆI[PXgtÉæé¥ÈðâIµÄ¢éBI[PXgÉÍtwÈÇ·yíêCÌ1`4N¶A¥ÍtwÈÆp¹ywÈÌ1`3N¶ªQÁBº\XgÍwàÌI[fBVÅè·éB
@2017N129úAæ50ñÌßÚÌèútïªJóê½BO¼Í`CRtXL[ÌoG¹yu¹ÌÎvAã¼Í^[Ìu}jtBJ[gvBI[PXgÍoCIât[gANlbgðwÔw¶ðͶßA²Æ¶A³õAGEtHjJÇ·ycÅÒ¬µAûüJõMEñíÎutªwöµ½Bu}jtBJ[gvÅÍA¯uÐO[NuªjºR[XÅÁíèA\XgÌtwÈ3NAOc ·©³ñª§¾´ éLÑâ©È\vmÅ£¹µ½(Ê^¶)BïêÝcâúÌótAU±àw¶Æ³EõªgíÁ½BܳɹywÌ1NÌW嬾B
@næÌPáCxgƵÄAyµÝɵĢét@རB±ÌúÍñ480lªlß©¯½BßÉZÞ«Íu20NÊO©çNÌæ¤ÉĢܷB¶Ìf°çµ¢¹yª±ñÈgßÅ®¯Ä 誽¢Å·vAvwÅÄ¢½«Íuã_dÔàÌLÅJÃðmÁÄAßÄܵ½B\XgÌ̺ªÆÄà«ê¢ÅfGŵ½B50ñౢĢéñÅ·ËvÆbµÄ¢½B
@¹ywÍ»ÝAlbqcnÅÌQÁ^tïulbJ^[rvâAbqïÙÅÌN3ñÌtïÈÇAnæÉ®ÌêðL°Ä¨èAçȶÝརB\XgÌOc³ñÍuä©çAú²ë¨¢bÉÈÁÄ¢énæÌûX̨窩¦ÄAÀSµÜµ½BS©çyµñÅ̤±ÆªÅ«Üµ½vÆAbµÄ¢½B
(Ä)
80üNLOvCxgúM@ÀkïuZå2@«êÒv\«ê©çpX|[gðg¦Ä[2017/12/28XV]


@1972NÈOÌAJ¡ºÌ«ê©çApX|[gðg¦ÄÉìqZúåw2Éiwµ½²Æ¶5¼ÆAåÍ´Êw@·A
ì¼Sw·ÉæéÀkïuZå2 «êÒv(Éìw@n§80üNLOvCxgúM)ª2017N1120úA}Ù2KO[oX^WIÅJ©ê½B
@Éìw@ÌZå2(éÔ)ÍA«Èªçwѽ¢w¶Ìj[Yɱ½¦A1950NÉJZBwÈðâí¸AèPÊð»ë¦êÎA³õƪæ¾Å«éÆ ÁÄAS©çw¶ªlß©¯½BÆèí¯Aíã̬ÌÅAwÑÌêªÀçêA³õÆÌ澪¢ï¾Á½«ê©çÌw¶ªÚ§Á½B
@A«ê©ç_Ë`ÜÅADÅ3A4ú©©Á½BÀÆð£êA«ÈªçÅàA2NųõƪæêéÌͣ;Á½B{yÖ̲êà Á½BÌpX|[gðQµ½îäõq³ñÍuAOÍ¢ëñȧñª èܵ½ªA«êÉÆÇÜÁÄÍ©·«Å«È¢L¢¢EðmÁ½±ÆÍA»ÌãÌl¶ÌÝÉÈèܵ½vƾ¤B
@5¼Sõª³õÆðæ¾µ½Bîä³ñÍA«ê§³çÏõïųçsêØÉß²µ½B¬wZ³õƵÄZ·ÜÅÎß½lAmðJuµA¡àgæ¶hð±¯élà¢éB
@5¼Ì¤¿4¼ªAÝwAÉOsÉ Á½A ééÆÅ«A¾â}oXÈÇAéÆÌT|[gð¾ÄÊwµ½B«êÆÉìw@̾¢ãJÌeÉÍA±¤µ½éÆÌæègÝà Á½æ¤¾B
@²Æ¶çÍuéÔÌwZÁÄåϾÁ½Åµå¤AƾíêéªAw×é±Æª¤êµASeÞw¶¶Åµ½vuÅàA°Ä¢A°èµ½ívu涪egÉkÉÌÁÄê½vÈÇAÎçÅv¢oðêÁ½Bu«êÅÖ¼ogÌlÉwÉ̲ƶÈÌxÆ¢¤ÆAw¢¢wZæËxÆÙßçêévAubq
êªerÉféÆAÉìw@ÌLª©¦Äw AêZªoÄéxƤêµÈèÜ·vÆAêZ¤à Óê½BåÍ´w@·ªu«ê©ç½Ìw¶ªÄêéæ¤AÍðݵÄÙµ¢vÆÄÑ©¯éÆAͤȸ¢½B
@Zå2Í1988NÉððI¦ÄÂwµ½BÀkïð©wµ½w¶©çÍuZåÉ2ª Á½±ÆÍmçÈ©Á½BÉÌðjð ç½ßÄ´¶½vÆ¢¤¦¼Èºª·©ê½B
@²Æ¶çÍñ50NÔèÌLpXð©ÄñèAu©ÂÄÌwÑÉâAFA¶tÌçªXÉv¢o³êÜ·vÆA´S[»¤ÉbµÄ¢½B
80üNLOvCxgúL@ÀkïuÀSEÀSðçév\x@¯ÌpqåêÌÀÍ[2017/12/19XV]


@x@¯Aòæ÷¯AxõïÐα\\BuÀSEÀSðçévEÆÉ]·é²Æ¶5¼ÆåÍ´Êw@·A
ì¼Sw·ÉæéÀkïuÀSEÀSðçév(Éìw@n§80üNLOvCxgúL)ª2017N1028úA}Ù2KO[oX^WIÅsíê½B
@ÉìqåwÌÁFÌêÂÉAx@¯Ìpl̽³ª é(©úV·oÅ@åwLO2018 qå1Ê)B±êͳçÚWuÐïÉv£Å«é«Ìç¬v̬ÊÅ èAɶÌܶßÅнޫÈCÌ\ê¾Bx@¯ÉÀç¸AuÀSEÀSvÉÖíétB[hÅô·é²Æ¶Í½¢B
@n[hÈ»êÉòÑñÅ¢´®ÍͽÈÌ©B
@²Æ¶©çÍuAJªZ(MFWI)ɯwµ½Æ«AÀSÉηéúÄÌÓ¯Ìá¢ðÄF¯µ½vuòwðwÔ¤¿AòÅ©élÌêûÅAòÅêµÞlª¢é±ÆðmÁ½vuåwÅ_¹ð±¯éÅAx@¯ðgßÉ´¶½vÆ¢¤ºª·©ê½BnæÌ«hÎNuÅô·éhÐmEäÖëq³ñÍulðv¢âèAx¦ ¤Éìw@ÌZÉÚµ½±ÆªA¡Ì{eBA¸_ÉÂȪÁÄ¢évƾ¢AåwEZåÅÌwѪ½ç©Ì`ÅEÆIðÉÑ¢Ģé椾B
@CtCxgÆ̼§Éàbèªyñ¾BuÀSEÀSvÉÖíéEÆÉA«Íܾh¾ªAEíÉæÁÄÍ«ª½¢BÅßÍ«ª«â·¢Â«®õàiñÅ¢éÆ¢¤Bu¥EoYðoÄ«±¯éæyª½¢ÌÅA»êɱ«½¢vu»êÅo±ðÏñ¾ ÆAqÇཿÖÌ[®É]µ½¢vÆA`¢ÍÀžõ¾B
@w¶ãÉâÁĨ¯Îæ©Á½±ÆƵÄAuL¢lÆÌð¬vð°é²Æ¶ªÚ§Á½BlXȧêâ«öÌlÉü«¤d¿A½lÈ¿lÏÉÚðJKv«ðÉ´·éÆ¢¤Bw¶©çuÉìqåwÌÝÍvÆâíêAuw¶ªS©çWÜÁÄ¢é±ÆªêÔÌ£ÍB¢ëñÈlÌl¦ÉGêé`XÆÆç¦ÄvÆAG[ðÁ½B
@ÀkïÅÍAx@¯ªìgpÌRcðÀµ½èAhÐmªèìèÌhЪÐðâI·éêÊ(Ê^¶)à èA²Æ¶çÌ^ÈpÉå«Èèªçê½B
(Ä)
nÍöl!?npðx¦é2ªÌ¼n[2017/10/30XV]



@ÉìqåwÉÍAqåÅÍ¿µ¢npª éB1967NnÌ` éNuB©OÌnêð½¸A©nÍ16NOÉwüµ½RJV(¤Ì:JAYA21Ë)1ª«èÆ¢¤¬Ñ¾Á½ªAðNA2ªÚÌnªÁíÁ½±Æ©çAlnÆàÉ`x[Vªã¸¾B2017N8ÉJ©ê½Ö¼w¶©nnpåïÌ᪢òz£ZÅA½ìMq³ñ(òwòwÈ4N)ªÀÝ¢éð}¦ÄDµ½B¯¶íÚÉoêµ½äÊسñ(SEÐïwÈ4N)à5ÊüÜðʽµAgV¶EnphðóÛt¯½B
@u©ªÅÍ«Ì¢oÅÍÈ©Á½ÌÅAܳ©DÈñÄcBn̨©°Å·vƽì³ñÍT¦ß¾Bõð°½nÍðNAV½ÉÁíÁ½R_YEF(¤Ì:_YAYA5Ë)B ê§ÌænNuŶÜêAnpÌûKnƵÄçÄçê½BgæynhÌJÍAàÆàÆnû£nÅôµ½TubhB·NABêÌûKnƵÄÉv£µA2015NAÖ¼w¶npA¿©çu÷JnvƵÄ\²³ê½BÌÍ̦ªSz³êÄ¢½ªAá¢_YªÁíÁ½±ÆÅAJÌSª¸èAõÌûKÊঽBåïÅÍAêÂÌíÚɯ¶nÍ2ñÜŵ©Gg[Å«È¢±Æ©çA±êÜŧÀ³ê½åïÖÌoêÌ`XàLªÁ½B
@^®nNuÅBêA¶«¨ðµ¤Ìªnp¾B»ÝAõÍ8lBnÍ_ËsºÉæÌe
StNuàÉ éænNuugDCNvÌXÉÉ¢é½ßAõ½¿Íåw©çñ1Ô©¯A¯NuÉÊ¢AnÌ¢bÆûKðµÄ¢éB
@XÉÅÒÂ2ªÌn̳CÈlqð©éÆAõ½¿ÍAÙÁƹðÈŨë·B³CÉ©¦ÄàA×ðТ½èAÜÉ΢۪üÁÄ}ÉÌÍð¸¤XNª èACª²¯È¢BSgÉuVð©¯Ä}bT[WµAïð¯AnêÉAêo·lqÍAÜéÅölð¢Æ¨µÞæ¤BnêÉoéÆAêl¸ÂænµÄAíà(ÈÝ µ)A¬à(Íâ µ)Aí«(©¯ µ)ð±ÈµAnÆÄzðí¹Ä¢B
@uLpXÉnêð¿A©nð10ªÈãø¦éåwª½¢ÅAsÈðÉß°¸Êðo¹½ÌÍA©MÉÂȪèܵ½vÆ¡{qqR[`;¤B©gàÉ̲ƶÅAnpÌæy¾B
@uæèèÉæÁÄAnÌ®«ªÏíéBnªæèèÌóÔð¦·o[^[ÉÈéñÅ·vÆ¡{R[`BnÌ«à éBJͪªæAæÅBSÒÉÍeؾªAµéÆÔxðêϳ¹AêààiñÅêÈ¢±ÆàB_YÍܾg[i[̲³BiñÅáQ¨Éü©ÁÄ¢áXµ³ªAæÌõÉÂȪÁ½Bõ½¿ÍnÌ@â²qÉUèñ³êȪçAu©ªÌw;¯ÅÍǤÉàÈçȢ̪AnpÌﵳŠèAʳB^ðb¦çêÜ·vÆAOü«¾B½ì³ñÆä³ñÍAåwÉüÁÄ©çnpðnß½BUèƳ꽱Æà1xâ2xÅÍÈ¢ªAuêxnß½çâßçêÈ¢£ZvÆAûð»ë¦éBuµÎçûKêÉs©È¢ÆAJâ_YÉÈèÜ·vBâÁÏèölÌ椾B@
(Ä)